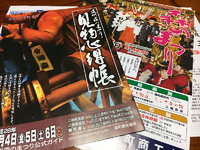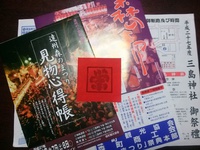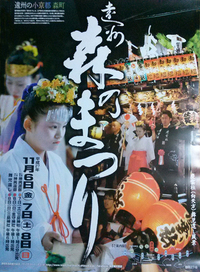2011年11月02日
遠州森のまつり・屋台編_14 「藤雲社(栄町)」
遠州森のまつり・お祭り前の話題。
森のまつりの屋台編、最終弾は、「藤雲社(栄町)」 です。
文中の絵 : 栄町・藤雲社/おかめひょっとこ
森町・下宿「佐藤看板店」 : 佐藤博志氏作
まずは栄町という町名、それから、藤雲社の社名の由来から。
 栄町通りの中心から、やや東に位置する「金守神社(通称:こんぴらさん)」。
栄町通りの中心から、やや東に位置する「金守神社(通称:こんぴらさん)」。
栄町の歴史は、この金守神社から始まると言っても、過言ではないでしょう。
江戸時代の頃、毎月17日の夜に人々が集まり金毘羅様を信仰したことから、この付近の部落は「十七夜」と呼ばれていました。 十七夜は、昭和初期までは非常に小さな部落で、水田がほとんどの地域でした。
下宿・桑水社、南町・湧水社の際にも記述したように、下川原町、下宿、五軒町、十七夜、角屋新田、忠エ門新田・・・ これらの地域は明治以降、「下宿」として桑水社の屋台を曳き廻していました。
昭和10年、国鉄・二俣線の遠江森駅(現在の天浜線・遠州森駅)が出来、昭和13年、それに伴って駅前大通り(現在の栄町通り)が完成。 下宿から独立した「栄町」という町が誕生しました。
以来、「下宿・栄町」として約50年間、桑水社の屋台を曳き廻したのです。
森駅が出来たことをきっかけに、栄町通りを中心に民家が増え始め、昭和40年代以降には、区画整理が次々に行なわれて水田が埋め立てられ、民家の戸数が飛躍的に増えていったことで、森地区で一番の大所帯となりました。
その後、昭和59年に栄町の南部地域が「南町」として分離独立。 南町は、桑水社から独立して、昭和60年に「湧水社」を設立。 同年、栄町も桑水社から独立して新たな社を設立することと、屋台を建築することが決定。 そして、二年後の昭和62年、「藤雲社」の屋台が落成したのです。
社名の由来は、金守神社・境内にそびえ立つ、樹齢400年以上と言われる楠木の大木に巻き付く「十七夜の大藤」にちなんでいます。 この大藤を龍にたとえ、龍が雲に昇るが如く、町内の躍進と幸福を願って命名されました。
藤雲社の加入により、森のまつりの参加町内は十四社となり、以来、三島神社・氏子社十社、準氏子社四社での屋台曳き廻しが行なわれています。
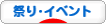
森のまつりの屋台編、最終弾は、「藤雲社(栄町)」 です。
文中の絵 : 栄町・藤雲社/おかめひょっとこ
森町・下宿「佐藤看板店」 : 佐藤博志氏作
まずは栄町という町名、それから、藤雲社の社名の由来から。
 栄町通りの中心から、やや東に位置する「金守神社(通称:こんぴらさん)」。
栄町通りの中心から、やや東に位置する「金守神社(通称:こんぴらさん)」。栄町の歴史は、この金守神社から始まると言っても、過言ではないでしょう。
江戸時代の頃、毎月17日の夜に人々が集まり金毘羅様を信仰したことから、この付近の部落は「十七夜」と呼ばれていました。 十七夜は、昭和初期までは非常に小さな部落で、水田がほとんどの地域でした。
下宿・桑水社、南町・湧水社の際にも記述したように、下川原町、下宿、五軒町、十七夜、角屋新田、忠エ門新田・・・ これらの地域は明治以降、「下宿」として桑水社の屋台を曳き廻していました。
昭和10年、国鉄・二俣線の遠江森駅(現在の天浜線・遠州森駅)が出来、昭和13年、それに伴って駅前大通り(現在の栄町通り)が完成。 下宿から独立した「栄町」という町が誕生しました。
以来、「下宿・栄町」として約50年間、桑水社の屋台を曳き廻したのです。
森駅が出来たことをきっかけに、栄町通りを中心に民家が増え始め、昭和40年代以降には、区画整理が次々に行なわれて水田が埋め立てられ、民家の戸数が飛躍的に増えていったことで、森地区で一番の大所帯となりました。
その後、昭和59年に栄町の南部地域が「南町」として分離独立。 南町は、桑水社から独立して、昭和60年に「湧水社」を設立。 同年、栄町も桑水社から独立して新たな社を設立することと、屋台を建築することが決定。 そして、二年後の昭和62年、「藤雲社」の屋台が落成したのです。
社名の由来は、金守神社・境内にそびえ立つ、樹齢400年以上と言われる楠木の大木に巻き付く「十七夜の大藤」にちなんでいます。 この大藤を龍にたとえ、龍が雲に昇るが如く、町内の躍進と幸福を願って命名されました。
藤雲社の加入により、森のまつりの参加町内は十四社となり、以来、三島神社・氏子社十社、準氏子社四社での屋台曳き廻しが行なわれています。
屋台の落成は、前述のとおり昭和62年。 二年後の平成元年には、塗り、金具の装飾なども完了し、大きさ、重量感、共に十四社中一、二を争うほどの屋台がお目見えしたのです。
この屋台の力量感を象徴するのは、その重厚な彫りもの。 湧水社に続き、北陸の彫刻師、福井・三国町の故・志村孝士氏が手掛けたもので、屋台前面が“七福神”で彩られるという、異色の作品。 この屋台の象徴と言えます。



彫刻の画材など、屋台の特徴に関しては、以前に紹介した「14町内の屋台“藤雲社”」に詳しく記載してありますが、前述した七福神、左右欄間の“龍”、支輪の“仙人”などの重厚感ある彫り、高欄下の板の裏側・「浜縁下」の“天女と鳳凰”の金蒔絵などで彩られ、優美、典雅という言葉が当てはまる屋台です。
更にもう一つ、藤雲社を象徴するものとして、どうしても挙げておきたいものがあります。 それは、文中の絵・佐藤博志氏の絵にも描かれている、「おかめひょっとこ」。 藤雲社は、「渡御」・「還御」の御渡りの際には、おかめとひょっとこに扮した若衆が、欄干に乗っててこ舞を披露します。
この「おかめひょっとこ」、屋台の先頭で陣頭指揮を取る「進行係」、社長以下「統制責任者」、「宮囃子」で優雅な演出をするお囃子、そして、勇壮且つ統制の取れた屋台の曳き廻し。 藤雲社は、これらの演出が評価されて、渡御の際に行なわれる「お囃子審査」で、平成元年から22年連続の一位という栄冠に輝いています。



湧水社と同じく、藤雲社は桑水社から分かれて独立した社ということで、桑水社を親社として敬っており、それは、「吉原継ぎに藤の花」の法被の柄にも表れています。 桑水社への思い入れは、藤雲社の社員としても、昔、桑水社の屋台を曳いた者としても、かなり強いものがあります・・・
以上、栄町・藤雲社の屋台に関する事を記してきましたが、歴史編と同じく、関係書物を参考にしたとはいえ独自視点での内容となりますので、確実性には欠けているかもしれませんので、下記の参考記事もご覧になって下さい。
これを持って、「森のまつり・屋台編」の特集記事は終了となります。
先週末には、屋台の飾り付けなど祭典準備も行なわれ、森町内は徐々にお祭りムードが高まってきています。 今年も、「絶対無事故」で楽しいお祭りが繰り広げられることを祈るばかりです・・・
遠州森のまつりまで、あと2日・・・
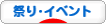
参考記事及び参考サイト
◇「森のまつり」14町内の歴史“藤雲社(栄町)”
◇「森のまつり」14町内の屋台“藤雲社”
◇「森の祭り・ホームページ」内 「各町内の屋台・藤雲社」
この屋台の力量感を象徴するのは、その重厚な彫りもの。 湧水社に続き、北陸の彫刻師、福井・三国町の故・志村孝士氏が手掛けたもので、屋台前面が“七福神”で彩られるという、異色の作品。 この屋台の象徴と言えます。
彫刻の画材など、屋台の特徴に関しては、以前に紹介した「14町内の屋台“藤雲社”」に詳しく記載してありますが、前述した七福神、左右欄間の“龍”、支輪の“仙人”などの重厚感ある彫り、高欄下の板の裏側・「浜縁下」の“天女と鳳凰”の金蒔絵などで彩られ、優美、典雅という言葉が当てはまる屋台です。
更にもう一つ、藤雲社を象徴するものとして、どうしても挙げておきたいものがあります。 それは、文中の絵・佐藤博志氏の絵にも描かれている、「おかめひょっとこ」。 藤雲社は、「渡御」・「還御」の御渡りの際には、おかめとひょっとこに扮した若衆が、欄干に乗っててこ舞を披露します。
この「おかめひょっとこ」、屋台の先頭で陣頭指揮を取る「進行係」、社長以下「統制責任者」、「宮囃子」で優雅な演出をするお囃子、そして、勇壮且つ統制の取れた屋台の曳き廻し。 藤雲社は、これらの演出が評価されて、渡御の際に行なわれる「お囃子審査」で、平成元年から22年連続の一位という栄冠に輝いています。
湧水社と同じく、藤雲社は桑水社から分かれて独立した社ということで、桑水社を親社として敬っており、それは、「吉原継ぎに藤の花」の法被の柄にも表れています。 桑水社への思い入れは、藤雲社の社員としても、昔、桑水社の屋台を曳いた者としても、かなり強いものがあります・・・
以上、栄町・藤雲社の屋台に関する事を記してきましたが、歴史編と同じく、関係書物を参考にしたとはいえ独自視点での内容となりますので、確実性には欠けているかもしれませんので、下記の参考記事もご覧になって下さい。
これを持って、「森のまつり・屋台編」の特集記事は終了となります。
先週末には、屋台の飾り付けなど祭典準備も行なわれ、森町内は徐々にお祭りムードが高まってきています。 今年も、「絶対無事故」で楽しいお祭りが繰り広げられることを祈るばかりです・・・
遠州森のまつりまで、あと2日・・・
参考記事及び参考サイト
◇「森のまつり」14町内の歴史“藤雲社(栄町)”
◇「森のまつり」14町内の屋台“藤雲社”
◇「森の祭り・ホームページ」内 「各町内の屋台・藤雲社」
Posted by 遠州森のビープロ at 00:23
[お祭り前の話題]
[お祭り前の話題]
この記事へのトラックバック
| <%PingExcerpt%> |
<%PingTitle%>【<%PingBlogName%>】at <%PingDateTime%>
この記事へのコメント
|
ビープロさん いつもおまつり情報をありがとうございます。 今年の書き込みである「遠州森のまつり・屋台編」をすべて読ませていただきました。 いよいよですね。 今年も藤雲社中老会・会所へ寄らせていただきますので よろしくお願いします。 |
Posted by 江戸前 at 2011年11月02日 08:24
|
江戸前さんへ いつも、コメントありがとうございます。 今年も、大晦日?を迎えて慌ただしくしてます。(^^ゞ いよいよ! という感じですね。 会所には、ぜひ遊びに来てくださいね! |
Posted by 遠州森のビープロ at 2011年11月03日 11:57
at 2011年11月03日 11:57
 at 2011年11月03日 11:57
at 2011年11月03日 11:57