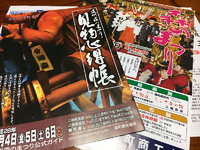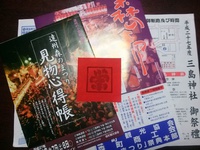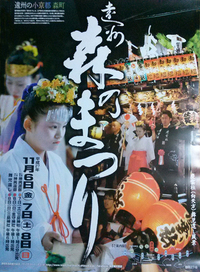2011年10月30日
遠州森のまつり・屋台編_13 「湧水社(南町)」
遠州森のまつり・お祭り前の話題。
森のまつりの屋台編、第十三弾は、「湧水社(南町)」 です。
文中の絵 : 南町・湧水社/竜とつばくろ
森町・下宿「佐藤看板店」 : 佐藤博志氏作
まずは南町という町名、それから、湧水社の社名の由来から。
 古くは明治の時代、現在の栄町地区の一部、五軒町、十七夜、角屋新田、そして、現在の南町に当たる忠エ門新田、新田、大柳・・・ これらの部落一帯は、当時は全て「下宿」でした。
古くは明治の時代、現在の栄町地区の一部、五軒町、十七夜、角屋新田、そして、現在の南町に当たる忠エ門新田、新田、大柳・・・ これらの部落一帯は、当時は全て「下宿」でした。
それから、昭和10年に国鉄・二俣線の遠江森駅(現在の天浜線・遠州森駅)が出来た際、上述の部落が下宿から独立して、「栄町」という町が出来ました。
その後、この地域は田畑が次々と埋め立てられて道路が整備され、民家の戸数が飛躍的に増えていき、結果、栄町は森町森地区一番の大所帯となりました。 人口はもちろん、面積も広範囲に渡っていたため、栄町の南部地域から新しい町内会を・・・ という声が挙がり、昭和59年、栄町から分離独立した「南町」が誕生したのです。
昔の部落名が示すとおり、現在の南町の地域は水田が多く、これは、昭和30年頃まで至る所で湧き水が見られたところから来ています。
私が子供の頃、この辺の水田一帯の水路に潜むザリガニ取りが子供たちの間で流行っていて、現在の天浜線のガードをくぐり、よく出掛けたものでした。
町の誕生の翌年の昭和60年、南町町民のシンボルとなる「湧水社」の屋台が誕生。 この年の湧水社の加入により、森のまつりの参加町内は十三社となり、二年後、藤雲社(栄町)の加入により十四社となるわけです。
社名の由来は、前述したように湧き水が多く見られたことから、その湧き水の如く人々が多く相集まり、団結して町内の発展を育んでいく・・・ ということから命名されました。
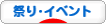
森のまつりの屋台編、第十三弾は、「湧水社(南町)」 です。
文中の絵 : 南町・湧水社/竜とつばくろ
森町・下宿「佐藤看板店」 : 佐藤博志氏作
まずは南町という町名、それから、湧水社の社名の由来から。
 古くは明治の時代、現在の栄町地区の一部、五軒町、十七夜、角屋新田、そして、現在の南町に当たる忠エ門新田、新田、大柳・・・ これらの部落一帯は、当時は全て「下宿」でした。
古くは明治の時代、現在の栄町地区の一部、五軒町、十七夜、角屋新田、そして、現在の南町に当たる忠エ門新田、新田、大柳・・・ これらの部落一帯は、当時は全て「下宿」でした。それから、昭和10年に国鉄・二俣線の遠江森駅(現在の天浜線・遠州森駅)が出来た際、上述の部落が下宿から独立して、「栄町」という町が出来ました。
その後、この地域は田畑が次々と埋め立てられて道路が整備され、民家の戸数が飛躍的に増えていき、結果、栄町は森町森地区一番の大所帯となりました。 人口はもちろん、面積も広範囲に渡っていたため、栄町の南部地域から新しい町内会を・・・ という声が挙がり、昭和59年、栄町から分離独立した「南町」が誕生したのです。
昔の部落名が示すとおり、現在の南町の地域は水田が多く、これは、昭和30年頃まで至る所で湧き水が見られたところから来ています。
私が子供の頃、この辺の水田一帯の水路に潜むザリガニ取りが子供たちの間で流行っていて、現在の天浜線のガードをくぐり、よく出掛けたものでした。
町の誕生の翌年の昭和60年、南町町民のシンボルとなる「湧水社」の屋台が誕生。 この年の湧水社の加入により、森のまつりの参加町内は十三社となり、二年後、藤雲社(栄町)の加入により十四社となるわけです。
社名の由来は、前述したように湧き水が多く見られたことから、その湧き水の如く人々が多く相集まり、団結して町内の発展を育んでいく・・・ ということから命名されました。
こちらの屋台、彫りものは北陸の彫刻師、福井・三国町の故・志村孝士氏が手掛けたもの。 昭和55年に、志村氏の作品が水哉社の屋台の彫りもので初めてお目見えしましたが、その次の作品として沿海社の彫りものの一部、そして、この湧水社の屋台に彩られたのです。



彫刻の画材など、屋台の特徴に関しては、以前に紹介した「14町内の屋台“湧水社”」に詳しく記載してありますが、この彫りものには、至る箇所に南町の“南”にちなんだ特徴が見られます。
まず、正面欄間の「風神雷神」の雷神がたたく太鼓には“南”という文字が、そして、左右側面の欄間には「波に麒麟」、後欄間には「波に龍」、すなわち三方向に波、“三波”となるわけです。
個人的には、屋台後方の高欄に付けられた、他社よりも一回り大きい町名看板が、この屋台の特徴の一つではないかと思っています。
金色の字で書かれた町名・・・ 北街社(新町)も同じように金字で町名が書かれていますが、黒地に金色の字、金色の縁取りは、それだけで豪華な彩りを添えているように見えます。
湧水社は、藤雲社と同じく、桑水社から分かれて独立した社であり、元々栄町であったということもあり、思い入れみたいなものというか、愛着はかなりあります。
法被の背、脇、袖に描かれた三本線も、桑水社の法被を継承しており、藤雲社同様、桑水社を親社として敬っていく・・・ そんな思いも感じられます。
以上、南町・湧水社の屋台に関する事を記してきましたが、歴史編と同じく、関係書物を参考にしたとはいえ独自視点での内容となりますので、確実性には欠けているかもしれませんので、下記の参考記事もご覧になって下さい。
遠州森のまつりまで、あと5日・・・
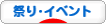
参考記事及び参考サイト
◇「森のまつり」14町内の歴史“湧水社(南町)”
◇「森のまつり」14町内の屋台“湧水社”
◇「森の祭り・ホームページ」内 「各町内の屋台・湧水社」
彫刻の画材など、屋台の特徴に関しては、以前に紹介した「14町内の屋台“湧水社”」に詳しく記載してありますが、この彫りものには、至る箇所に南町の“南”にちなんだ特徴が見られます。
まず、正面欄間の「風神雷神」の雷神がたたく太鼓には“南”という文字が、そして、左右側面の欄間には「波に麒麟」、後欄間には「波に龍」、すなわち三方向に波、“三波”となるわけです。
個人的には、屋台後方の高欄に付けられた、他社よりも一回り大きい町名看板が、この屋台の特徴の一つではないかと思っています。
金色の字で書かれた町名・・・ 北街社(新町)も同じように金字で町名が書かれていますが、黒地に金色の字、金色の縁取りは、それだけで豪華な彩りを添えているように見えます。
湧水社は、藤雲社と同じく、桑水社から分かれて独立した社であり、元々栄町であったということもあり、思い入れみたいなものというか、愛着はかなりあります。
法被の背、脇、袖に描かれた三本線も、桑水社の法被を継承しており、藤雲社同様、桑水社を親社として敬っていく・・・ そんな思いも感じられます。
以上、南町・湧水社の屋台に関する事を記してきましたが、歴史編と同じく、関係書物を参考にしたとはいえ独自視点での内容となりますので、確実性には欠けているかもしれませんので、下記の参考記事もご覧になって下さい。
遠州森のまつりまで、あと5日・・・
参考記事及び参考サイト
◇「森のまつり」14町内の歴史“湧水社(南町)”
◇「森のまつり」14町内の屋台“湧水社”
◇「森の祭り・ホームページ」内 「各町内の屋台・湧水社」
Posted by 遠州森のビープロ at 08:57
[お祭り前の話題]
[お祭り前の話題]
この記事へのトラックバック
| <%PingExcerpt%> |
<%PingTitle%>【<%PingBlogName%>】at <%PingDateTime%>
この記事へのコメント
|
あっと言う間の一年でした(^-^) あの日から一年経って、今は中老一年生。。 なんか今年はゆるせく祭りを楽しめそうで、今までとは違うわくわくが止まりません! 今年もよろしくです(^o^)v |
Posted by ともっち at 2011年10月30日 20:10
|
ともっちさん、ご無沙汰です。m(__)m 若衆集大成から、早や一年ですね。 中老は、町内にもよりますが、10年ぐらいはゆるせいですよ。(^.^) しばらくの間は、充分に楽しんでくださいね! 今年も、中老会の会所に居るんで、よかったら寄ってくださいね。(^^)v |
Posted by 遠州森のビープロ at 2011年10月31日 01:22
at 2011年10月31日 01:22
 at 2011年10月31日 01:22
at 2011年10月31日 01:22