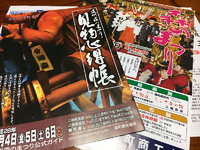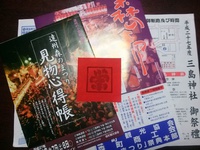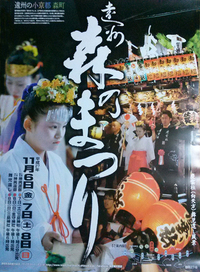2011年10月05日
遠州森のまつり・屋台編_5 「北街社(新町)」
遠州森のまつり・お祭り前の話題。
森のまつりの屋台編、第五弾は、「北街社(新町)」 です。
文中の絵 : 新町・北街社/司馬温公 瓶割り小僧
森町・下宿「佐藤看板店」 : 佐藤博志氏作
まずは新町という町名、それから、北街社の社名の由来から。
 新町というと、新しく出来た町というイメージが沸きますが、江戸時代初期の森町村設立時からあった町だと伝わっています。
新町というと、新しく出来た町というイメージが沸きますが、江戸時代初期の森町村設立時からあった町だと伝わっています。
森町村が出来た当時は、村を上町と下町として二つに町割し、その後、上新町(現在の新町)と下新町(後に旅籠町と呼ばれる現在の本町の一部)が出来、更に町割が行なわれ、下側から本町、中町、横町、新町となったわけです。
本町や中町などと同様に、新町は旅籠屋、呉服屋、古着屋、質屋などの商家が軒を連ね、裏通りには何軒もの蔵が立ち並ぶ、まさに栄華を誇るというに相応しい栄えた町でした。
私が子供だった昭和40年代、50年代も商店街は賑やかで、夏に行なわれる歩行者天国では、横町通り(中央通り)と新町通りが一番人の出も多く、活気に満ち溢れていたことを覚えています。
現在では、前述の本町、仲横町同様、商店の数も減り、もの寂しい雰囲気になったことは否めませんが、本町通りから続く筋かった通りや、蔵が残る裏通りを歩いてみると、情緒さえ感じることも出来ます。
社名の由来は、旧森町村の一番北に位置していたことから命名されたと伝わっています。 北に位置する、森町村の市街地であった新町に相応しい社名だと言えると思います。
屋台は、現在のものが4代目だと思われます。
初代の屋台は、製作年は不明ですが、桑水社や水哉社、沿海社、そして比雲社と共に江戸末期には、現在のような形の屋台で曳き廻されていたことは確かです。 2代目の屋台は、明治26年に製作され、昭和3年まで曳き廻されました。 そして、昭和4年に先代の屋台が新築され、こちらは平成3年まで曳き廻され、その後、森町・飯田地区の若宮町内会に売却、現在も活躍中です。
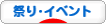
森のまつりの屋台編、第五弾は、「北街社(新町)」 です。
文中の絵 : 新町・北街社/司馬温公 瓶割り小僧
森町・下宿「佐藤看板店」 : 佐藤博志氏作
まずは新町という町名、それから、北街社の社名の由来から。
 新町というと、新しく出来た町というイメージが沸きますが、江戸時代初期の森町村設立時からあった町だと伝わっています。
新町というと、新しく出来た町というイメージが沸きますが、江戸時代初期の森町村設立時からあった町だと伝わっています。森町村が出来た当時は、村を上町と下町として二つに町割し、その後、上新町(現在の新町)と下新町(後に旅籠町と呼ばれる現在の本町の一部)が出来、更に町割が行なわれ、下側から本町、中町、横町、新町となったわけです。
本町や中町などと同様に、新町は旅籠屋、呉服屋、古着屋、質屋などの商家が軒を連ね、裏通りには何軒もの蔵が立ち並ぶ、まさに栄華を誇るというに相応しい栄えた町でした。
私が子供だった昭和40年代、50年代も商店街は賑やかで、夏に行なわれる歩行者天国では、横町通り(中央通り)と新町通りが一番人の出も多く、活気に満ち溢れていたことを覚えています。
現在では、前述の本町、仲横町同様、商店の数も減り、もの寂しい雰囲気になったことは否めませんが、本町通りから続く筋かった通りや、蔵が残る裏通りを歩いてみると、情緒さえ感じることも出来ます。
社名の由来は、旧森町村の一番北に位置していたことから命名されたと伝わっています。 北に位置する、森町村の市街地であった新町に相応しい社名だと言えると思います。
屋台は、現在のものが4代目だと思われます。
初代の屋台は、製作年は不明ですが、桑水社や水哉社、沿海社、そして比雲社と共に江戸末期には、現在のような形の屋台で曳き廻されていたことは確かです。 2代目の屋台は、明治26年に製作され、昭和3年まで曳き廻されました。 そして、昭和4年に先代の屋台が新築され、こちらは平成3年まで曳き廻され、その後、森町・飯田地区の若宮町内会に売却、現在も活躍中です。
そして平成4年、豪華絢爛な美しすぎるほどの、現在の屋台が落成されました。 先代の屋台の造りを継承しながらも、モダンなデザインと言える造りが随所に見られ、観ているだけでも、その美しさには魅了されます。
文中の絵・佐藤博志氏の絵にも描かれている、正面欄間の「司馬温公・瓶割り小僧」、左右の御簾脇の「風神・雷神」、脇障子の「松に干し網」、これらの彫りは、先代の屋台から継承したものです。



北街社の屋台の特徴として、特筆すべきなのは正面の欄干。
北街社の欄干は真ん中が開いていて、これも先代の屋台から受け継がれているもの。 これは、神社の本殿の欄干の正面が、神様の出入りのために開けていることに倣ったもので、十四社中、北街社だけの特徴です。
舞児還しでは、北街社は欄干真ん中に乗る舞児のみが立ち、両側に乗る社長と氏子総代(もしくは浦安稚児担当)は座って乗ります。
これは、舞児をひと際目立たせるためというのと同時に、舞児が開いている欄干から落ちないように、両側から支えるための配慮ということでもあります。
そして、もう一つの特徴として挙げておきたいのが、軽快なお囃子と素早い屋台の曳き廻し。 太鼓の皮の質や叩き方などで、お囃子を聴いただけでどこの社の屋台が来たか、地元民であればある程度は分かるのですが、北街社の軽快なお囃子は特に分かりやすく、屋台の曳き廻しも、現在の大きな屋台を素早く曳き廻すという芸当は、やはり昔から受け継がれている、北街社の伝統と言えるかと思います。
以上、新町・北街社の屋台に関する事を記してきましたが、歴史編と同じく、関係書物を参考にしたとはいえ独自視点での内容となりますので、確実性には欠けているかもしれませんので、下記の参考記事もご覧になって下さい。
遠州森のまつりまで、あと30日・・・
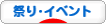
参考記事及び参考サイト
◇「森のまつり」14町内の歴史“北街社(新町)”
◇「森のまつり」14町内の屋台“北街社”
◇「森の祭り・ホームページ」内 「各町内の屋台・北街社」
文中の絵・佐藤博志氏の絵にも描かれている、正面欄間の「司馬温公・瓶割り小僧」、左右の御簾脇の「風神・雷神」、脇障子の「松に干し網」、これらの彫りは、先代の屋台から継承したものです。
北街社の屋台の特徴として、特筆すべきなのは正面の欄干。
北街社の欄干は真ん中が開いていて、これも先代の屋台から受け継がれているもの。 これは、神社の本殿の欄干の正面が、神様の出入りのために開けていることに倣ったもので、十四社中、北街社だけの特徴です。
舞児還しでは、北街社は欄干真ん中に乗る舞児のみが立ち、両側に乗る社長と氏子総代(もしくは浦安稚児担当)は座って乗ります。
これは、舞児をひと際目立たせるためというのと同時に、舞児が開いている欄干から落ちないように、両側から支えるための配慮ということでもあります。
そして、もう一つの特徴として挙げておきたいのが、軽快なお囃子と素早い屋台の曳き廻し。 太鼓の皮の質や叩き方などで、お囃子を聴いただけでどこの社の屋台が来たか、地元民であればある程度は分かるのですが、北街社の軽快なお囃子は特に分かりやすく、屋台の曳き廻しも、現在の大きな屋台を素早く曳き廻すという芸当は、やはり昔から受け継がれている、北街社の伝統と言えるかと思います。
以上、新町・北街社の屋台に関する事を記してきましたが、歴史編と同じく、関係書物を参考にしたとはいえ独自視点での内容となりますので、確実性には欠けているかもしれませんので、下記の参考記事もご覧になって下さい。
遠州森のまつりまで、あと30日・・・
参考記事及び参考サイト
◇「森のまつり」14町内の歴史“北街社(新町)”
◇「森のまつり」14町内の屋台“北街社”
◇「森の祭り・ホームページ」内 「各町内の屋台・北街社」
Posted by 遠州森のビープロ at 09:19
[お祭り前の話題]
[お祭り前の話題]
この記事へのトラックバック
| <%PingExcerpt%> |
<%PingTitle%>【<%PingBlogName%>】at <%PingDateTime%>